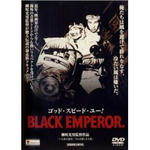
「ゴッド・スピード・ユー! BLACK EMPEROR」鑑賞。
ポストロックの中でも「スロー・コア」の第一人者である、この映画と同名のバンドが存在するが、この映画にインスパイアされて名前をパクったらしい。
うわー久しぶりにバイク乗りたくなりました。
ぼくがいつも映画とか本とかPCとか音楽とかばっかりやっているひきこもりだから、友達少ないんだろうなーとか思っているヤツ!!!
ぶぶー。不正解。
地元のスケボースノボーチーム「神風」代表です。
よく
ダチの
単車の後ろに乗って、真夜中のバンナグロ街道を100キロで駆け抜けます。
ヘイヘイヘーイ!!!!
んなこたあどうでもいいんだけど、
1976年に作られた、暴走族「黒い皇帝」のドキュメンタリー映像です。
かなり彼らに密着した映像だったので、どうやって撮ったの!?カンジ。
組織とか、リーダーシップとか、カリスマとか、いろんなことを考えました。
まず、集会を取り仕切るリーダーの言動は20歳そこらとは思えないほど、とても説得力があって、カリスマ性に満ちあふれている。
公道で警察となんども口論するシーンがあるのだが、警察よりも彼らの口調の方が論理的で明快だったりして、どっちが大人なのかわからないよwって思った。
この映画から学び取る要素はたーっくさんあるように思う。
っていうか、音楽の入れ方とか、カッコイイし。
暴走族最高!!!!!!!
たぶん現代人は、バイアスだらけのガチガチ人間なので、こんな30年前の映画なんて見ないし。
そこでピックアップされる暴走族の19歳の人間なんてクズだとか思うんでしょうが、
てめえらの方がよっぽどクズです。
度胸、リーダーシップ、発言力、どれをとっても現代のいわゆる普通の人よりグレードは高い。
家族ともシッカリ話すし。エライ。
「昔の暴走族はノータリンで恐ろしい生き物だ」なんてのは、偏見そのものですな。
なんか最近ぼく、バイアスって言葉連発してますが、ホント大事だと思います。
バイアス。
僕は、多分札幌一バイアスの無い人間だと自負しております。
柔軟そのもの。フニャチン。
だから、どんな事に対してもふにゃふにゃに受け止めるし、そこからイイとこだけを抽出してラーニングします。
そういうスライムのような生き方です。
ぼく、北大の人はあまり好きではありません。
まあ北大の人全部を偏見の対象にするのは、それこそアホなんですが、割合で見て、バイアスがやばい。
基本「自分は頭がいい。偉い。」と勘違いしている。
北大に入るようなやつに限って、友達がものすごい少なかったりするんですが、それって人を割と見下しているからだと思うし、なんか柔軟じゃないんですよねー。
ファッションもダサイ。
なにも学び取る要素がない。
それに比べて地元の友達はとっても打ち解けていて、おちゃらけていて、楽しいんです。
頭もいい。
大事なのって、非日常をいかに生きているかだと思う。
「あたしそういうのわからないから・・・」
「僕、そういう人じゃないから・・・・」
ファアアアアーーック!!!!!!!!!
お前ら自分がどんな人間か完全に把握してんの!?!?!?!?!?
コワ!!!!!
ぼくは自分が全く分かりません。
何しでかすかわかりません。ww
まず幅が広すぎるし、深すぎる。
把握しきれません。
人って無限だと思うし、だから哲学者や文学者一人を大勢の人が生涯をかけて研究したりするんでしょう!?!?!?!??
人を動かすのは人にしかできない。
だからぼくは、みんな一人一人無限だと思っています。
「こいつと話していても話すネタがつきる・・・・。」
とかありえないと思います。
一人の人と一生語り続けるとか、余裕だと思います。
少なくとも、しょうとか目田村さんとかトモミとかとはずーーーーーっと話せる予感!!!
はい書き過ぎ調子のりすぎ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
PR

無題
2007/12/03(Mon)03:41
ジャンルなんてどうでもいいんだけど。
ポスト・ロックってこれからの分野ですね。
音のオナニスト的側面と音の開拓者的側面をどう表現者の中で必然的に結び付けるか、ということがポスト・ロックの最大の課題ですね。
トータスがポスト・ロックの代表だと思うのはやっぱりその問題と闘い続けてるからだと思うからです。
ジョン・マッケンタイアが「俺はポスト・ロックという言葉になんらポジティブな要素を見いだせない」だとか「俺たちはただのインストゥルメンタルバンドだ」とか言う発言は、アウトサイダーになりたいアーティストの戯言ではなく、ポスト・ロックというジャンルの難しさをもっとも体言している男の悲痛な叫びとして受け取るべきです。
俺はしばしばロック原理主義者と考えられがちだけど、そしてそれは間違いではないけれど、ポスト・ロックに多大な期待を寄せています。
しかし、さきほど述べた問題をポスト・ロック自身が自覚しなければただの、快楽主義的な音になってしまう。別に快楽主義的な音楽を否定してるわけではありません。
大好きなZepは快楽主義的な側面もあるし。
ただ快楽主義のみでいくとポスト・ロックというある種捏造されたジャンルである意味が、存在する意味が全くないということです。
つっても、へヴィメタの快楽主義の数千倍ましではあるけど。
音に言葉を付加する以外のメッセージ伝達方法の確立をポスト・ロックに期待します。
俺の大好きなシガーロスは中間領域の音楽です。
これは昔書いた論文で、どこにも発表してないけど、端的に言えばこういうものです。
言葉はあるけれど自分たち以外の誰にも伝わらない音楽である。
それはオナニスト的側面も存在しているが、言葉がある、無いの中間に新しい表現方法を見出し、それを必然化する開拓者的側面を持った音楽の創造。
これこそポスト・ロックと呼ばれてしかるべき音楽。
ヨンシー(ジョンジー)のボウイング奏法を聴いて同じボウイング奏法を使用したZepのギタリスト、ジミー・ペイジの「幻惑されて (Dazed and Confused)」を思い出したのは偶然ではなく必然的な通底関係な気がします。
ポスト・ロックがロックであるように、ロックはポスト・ロックであり続けたという示唆。
つまりポスト・ロックの問題点として挙げたものはそのままロックの問題点にもなり得るということです。
ただ一言間違いなく言えるのは、ポスト構造主義が構造主義を消し去るものでないように(結構いるんだよなあ、ここを勘違いしてる人が。それが違うってことはドゥルーズとかデリダ読めばわかるはずだが。デリダによるレヴィ・ストロース批判なんか批判になりきってないことくらい)、ポスト・ロックがロックを消し去ることなんか無いように。
それを今年、ブルース・スプリングスティーンとベイビー・シャンブルズを聴いて思った。
友達と飲み会して三時間後に書いた記事です。酒はなかなか脳を活性化させるんだなあ。
No.1|by メタムラサキ|
URL|Mail|Edit